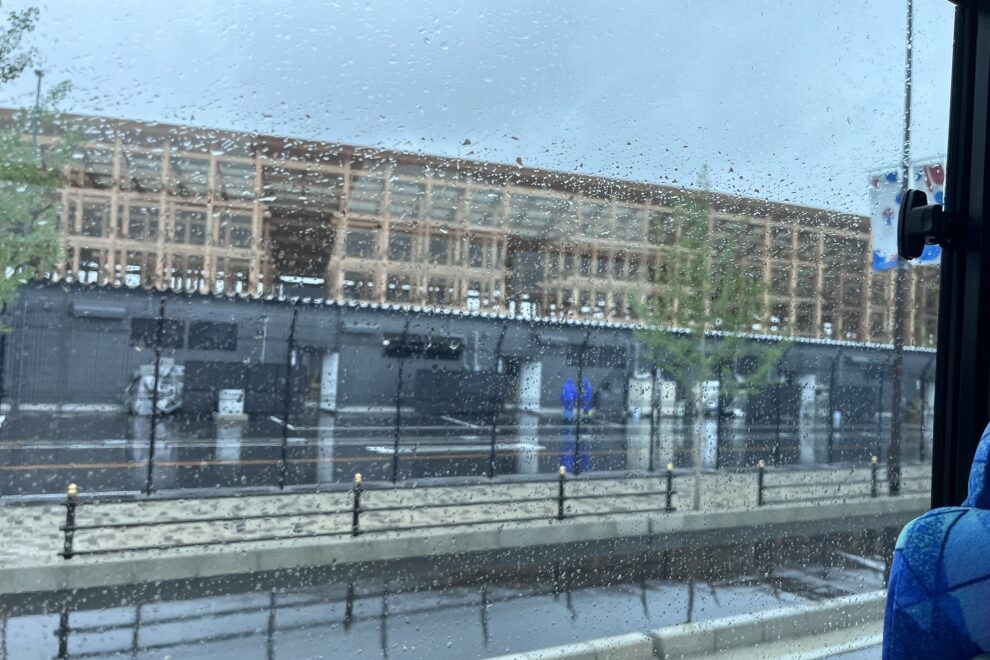
雨の降る中、ゴールデンウィークに「EXPO2025 大阪・関西万博」へと足を運んだ。
目的は、会場で新しい技術がどのように取り入れられ、試されているのか、その一端に触れることである。
本記事では、そこで体験したデジタル技術関連の試みを中心に報告したい。
今回は家族(妻、小学生の息子2人)を伴っての訪問であり、必ずしも純粋な取材環境とは言えなかったが、その状況も含めてお伝えできればと思う。
デジタルウォレット「ミャクペ!」体験
万博体験において重要な役割を担うのが、「EXPO2025デジタルウォレット」だ。このウォレットが持つ機能と、それによってどのような体験ができるのか、実際に試してみた。
会場に着いてまず利用したのは、ウォレットの決済機能「ミャクペ!」である。1杯3850円の「神戸牛すき焼きえきそば」が話題のお店にて、弁当を購入することにした。

店員さんに「ミャクペで」と伝えると、専用のQRコードが提示された。
それをスマホで読み取ることで、支払いはスムーズに完了。このミャクペ!は、既存のキャッシュレス決済と近いユーザーインターフェースで、利用者にとっては馴染みやすい操作性となっている。

次に「デジタルウォレットパーク」を訪れた。

ここはEXPO2025デジタルウォレット関連機能の中心となる施設だ。
このデジタルウォレットは、「つかう/ためる/あつめる」として、決済サービス「ミャクペ!」(つかう)、ポイントサービス「ミャクポ!」(ためる)、デジタルアイテム(NFT)サービス「ミャクーン!」(あつめる)があり、さらに「つながる」として事業連携サービスがある。
「つかう/ためる/あつめる」に対しては、ウォレットにはリンクが設定されており、いわばポータルのような役割になっている。ウォレットのコア機能は、事業連携サービスとしての「ミャクミャクリワードプログラム」と、後述する「EXPOトークン」だ。
ミャクミャクリワードプログラムは、ウォレット内での特定の行動──ミャクペ!へのチャージ(1円相当につき1expを付与)や指定ミッションの達成など──に応じて「経験値(exp)」が貯まり、その蓄積量によってユーザーのステータスが変動、ステータスに応じた特典が得られるというもの。ゲーミフィケーションの考え方が取り入れられている。
筆者の万博訪問時のステータスは「ゴールド」で、最上位のレジェンド特典であるミャクミャクとの記念撮影などにはまだ手が届かない。

ウォレットパークの奥では、おそらくレジェンドの方なのだろう、ミャクミャクと楽しそうに記念撮影をしている人影が扉の向こうにチラリと見えた。正直、かなり羨ましかった。expを貯めるモチベーションが、ああいった形で可視化されるのは面白い試みだと感じた。
そして、このデジタルウォレットには、「EXPOトークン」と呼ばれる、万博独自の電子マネー(またはポイント)のようなものが存在する。
あまり聞き慣れない言葉かもしれないが、これは1コイン1円相当として、「ミャクペ!」にチャージすることで、タッチ決済対応のVisa加盟店および「iD」に対応した店舗で利用可能となっているものだ。
万博に関わる活動への参加を通じて獲得できるほか、本人確認済みのSBT(ソウルバウンドトークン、譲渡不可能なNFT)デジタルパスポートを持つユーザー間送金も可能となっている。
将来的には海外からの来場者向けに、米ドル連動のステーブルコインUSDCとの交換機能も計画されているという点も付け加えておきたい。
筆者も、万博訪問後に友人紹介キャンペーンを通じて100EXPO(100円相当)がウォレットに付与された。

NFTとパビリオン巡り、万博会場のリアルな空気
このEXPOトークンを実際に街ナカの店舗で利用してみた体験は、後ほど詳しく触れたい。
デジタルアセットの収集も体験した。複数のパビリオンを巡り、NFT形式のスタンプラリーを数カ国分集めたほか、SBTとしてのデジタルパスポートも発行された。

現時点では収集を楽しむことが主目的のようだが、こうしたデジタルな記念品が今後どのように活用されていくのか、一つの流れとして見ていきたい。
なお、NFTスタンプラリーを効率よく集めるには、各国のナショナルパビリオンが集まる「コモンズ」エリアが良いだろう。
ちなみに、同行した次男は従来型の紙のスタンプラリーに夢中になっており、これはデジタルと物理的な体験が混在する今の時代ならではの光景かもしれない。

気になるパビリオンと万博会場の雰囲気
メディアアーティスト落合陽一氏が手がけるシグネチャーパビリオン「null²」にも足を向けた。
しかし、ゴールデンウィーク期間中の会場は大変な混雑で、当日の予約枠確保は難しく、残念ながら今回は見送ることとなった。加えて、同行した次男は独特な外観にビビっていた。

とはいえ、万博の魅力は多岐にわたる。
会場を歩けば、多様な文化や未来社会に対する様々な視点が目に飛び込んでくる。
ポルトガル、サウジアラビアなどのパビリオンや、印象的だった輪島塗大型地球儀「夜の地球 Earth at Night」といった展示の数々を見比べるのは、それだけでも心が騒ぐ体験だ。
また、万博のシンボルとも言える木造の大屋根リングを歩けば、会場全体を俯瞰でき、この国際的なイベントの一体感を感じ取ることができた。

EXPOトークン、取引所を介さず日常の「円」決済へ
ウォレットに付与された100EXPO。このEXPOトークンには、特筆すべき実用性がある。
それは、万博会場外の店舗でも決済に使えるという点だ。
後日、早速その実力を試すべく、筆者の地元・京都のファミリーマートへ。仕事終わりの”一杯”を購入するためだ。レジに進み、EXPO2025デジタルウォレットを起動。
今回はiDでの支払いを試みることに。店員さんに「iDで」と伝え、スマホを決済端末にかざす。決済音が鳴り、無事チューハイをゲット。
「EXPOトークンでチューハイが買えた!」という、ちょっとした感動と達成感があった。

この体験で特に印象的だったのは、獲得したEXPOトークンが、暗号資産取引所を通さずに、普段の「円」での支払いとして近所のコンビニで手軽に使えたことだ。
ユーザーは特別な知識や手続きをほとんど必要とせず、トークンを電子マネー「ミャクペ!」にチャージするだけで、既存の決済ネットワーク(VisaやiD)に乗せることができる。
これは、新しい形のデジタルポイントや地域通貨が、よりスムーズに実社会の経済活動に接続される一つの方法を示しているのかもしれない。
なお、EXPO2025デジタルウォレットは、Aptos Networkのブロックチェーンを基盤技術として採用しており、EXPOトークンもこの上で発行・管理されている。

万博体験の総括と、これから行く人へのヒント
今回の万博で触れたデジタル技術関連の試みは、まさに「実験場」という言葉がふさわしく、様々なアイデアが形になりつつある過程を見ているようだった。
今回は「Web3体験」を一つの目的に掲げて万博へ臨んだ。
しかし、大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」という大きなテーマを掲げており、デジタルウォレットやそれに関連するEXPOトークン、NFTスタンプラリーといった試みは確認できたが、来場者が直接的にブロックチェーン技術やWeb3に触れられる展示やサービスは、現時点では限定的であるように感じられた。
しかし、一方で意外な気づきもあった。
例えば、スタンプラリーをはじめ、会場の案内表示のあちこちで「NFT」という言葉を目にしたことだ。

これは、一般層におけるNFTという言葉の認知度が、我々が思っている以上に高まっている可能性を示唆しているのかもしれない。
そして、EXPOトークンである。
前述の通り、これを日常の買い物で利用できた体験は非常に印象的だった。
取引所を介さずにデジタルな価値が円決済として使える手軽さは、今後のイベントや地域活動におけるデジタル活用の参考になるかもしれない。
最後に、今回の体験を踏まえ、これから万博を訪れる方へ、いくつかお伝えしたいことがある。Facebookで流れてきて共感した「万博ノウハウ」も交えて紹介したい。
まず、「1回目は下見と思うべし」という心構え。広大な会場と多数のパビリオンを1日で全て網羅するのは難しい。特に人気の大国パビリオンは予約なしでの入場は困難だ。
そして、「モバイルバッテリーは必須」という点。これは筆者自身が痛感したことでもある。
午前10時に会場入りし、パビリオンの予約手続き、マップ確認、NFTスタンプラリー、ミャクペ決済、写真撮影と、あらゆる場面でスマホを酷使した結果、午後2時頃にはバッテリーが尽きてしまったのだ。
スマホが機能しなくなると、「何もできない」状態に陥ってしまう。大容量のモバイルバッテリーと充電ケーブルは、まさに生命線だ。紙のマップをプリントアウトして持参すると良いだろう。会場では紙のマップの配布はない。
ここに全体マップをダウンロードできる公式リンクを貼っておく。
会場の歩き方の一つとして、巨大な木のリング(大屋根)の上から会場全体を見渡し、レイアウトを把握するのも良いだろう。もちろん、「EXPO2025デジタルウォレット」の事前準備も忘れずに。
最後に、これは筆者の個人的な体験からのアドバイスになるが、万博の楽しみ方について少し。
会場内には子ども向けの遊具施設なども用意されているが、パビリオンの展示内容となると、最先端技術や社会的なテーマを扱ったものが多く、正直なところ、我が家の息子たち(小学5年と3年。決して小さいわけではないのだが…)は、すぐに飽きてしまった。もちろん、これはあくまで我が家の場合であり、展示の楽しみ方は人それぞれだ。
ただ、もし万博の深いテーマ性や技術的な側面をじっくりと堪能したいのであれば、一度目は家族でワイワイと雰囲気を楽しみ、興味が湧けば、二度目は一人、あるいは大人同士で訪れてみる、というのも一つの手かもしれない。
そうすれば、子どもたちのペースを気にせず、自分の関心のある展示に時間をかけて向き合えるだろう。現に筆者は、次こそは一人でじっくりと、と画策している。もっとも、次男からは「スタンプ代わりに押してきて」と、本人はもう完全に行く気がない口ぶり…。
今回の万博訪問は、まさに壮大な「実験場」の一端を垣間見たものであった。
開幕前には様々な声も聞かれたが、実際に足を運んでみると、EXPOトークンのような新しい試みや、各所で展開されるデジタル技術を駆使した展示・サービスに触れる体験は、やはり刺激的であった。まさに百聞は一見にしかず、である。
本記事で紹介した体験や「歩き方のヒント」が、CoinDesk JAPANの読者の皆さんが大阪・関西万博を訪れ、その未来の片鱗を楽しむための一助となれば幸いである。
|文:栃山直樹
|画像:筆者撮影


